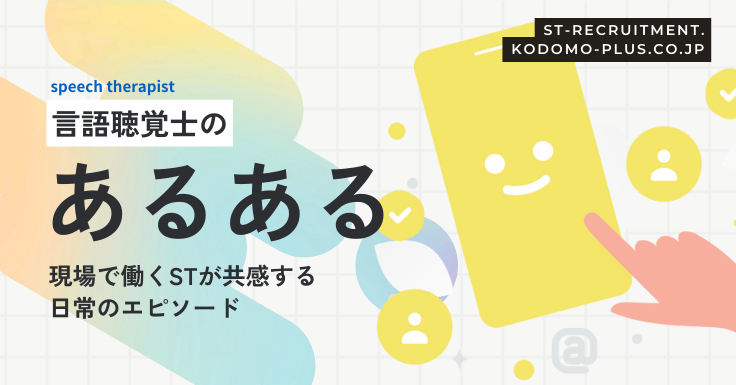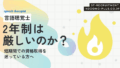言語聴覚士として働いていると、他の職種には理解されにくい独特な体験をすることがあります。
患者さんとのやり取りや職場での出来事など、言語聴覚士ならではの「あるある」エピソードは、同じ職業の方なら思わず「わかる!」と頷いてしまうものばかりです。
今回は、現場で働く言語聴覚士の皆さんが日々経験している、リアルで親しみやすい「あるある」エピソードを厳選してご紹介します。
新人STの方から経験豊富なベテランまで、きっと共感できる内容が見つかるはずです。
患者さんとの関わりでよくある言語聴覚士あるある
言語聴覚士の仕事の中心となる患者さんとの関わりには、特有の面白あるあるエピソードがたくさんあります。
コミュニケーション障害を専門とする職種だからこそ生まれる、心温まる場面や思わず笑ってしまう出来事をまとめました。
失語症の患者さんとの心通じる瞬間
失語症の患者さんとの訓練では、言葉以外のコミュニケーションが重要になることが多いとされています。「りんご」という単語が出てこない患者さんが、手で丸い形を作って「赤い、甘い」と一生懸命説明してくれる姿に、言葉の奥深さを感じる言語聴覚士は少なくありません。
患者さんが久しぶりに「ありがとう」と言葉で伝えてくれた瞬間は、多くの言語聴覚士が経験する感動的な場面です。その一言のために何ヶ月も訓練を重ねてきた成果を実感できる、この職業ならではの喜びと言われています。
構音障害の訓練で起こるユニークな場面
構音障害の訓練では、舌の動きや口の形を細かく指導することが必要です。「た・て・と・つ・と」の練習中に、患者さんと一緒に必死に舌を動かしていたら、通りかかった看護師さんに変な目で見られてしまったという経験は、多くの言語聴覚士が持っているエピソードです。
鏡を見ながら口の動きを確認する訓練では、患者さんと二人で変顔の練習をしているような状態になることもあります。真剣にやっているのに、客観的に見ると少し面白い光景になってしまうのは、構音訓練ならではの特徴と言えるでしょう。
患者さんとのやり取りから生まれるこれらのあるあるエピソードは、言語聴覚士という職業の魅力でもあります。
次に、職場内での同僚や他職種との関わりで起こる「あるある」について見ていきましょう。
職場での他職種連携にまつわる言語聴覚士あるある
言語聴覚士は医療チームの一員として、医師や看護師、理学療法士、作業療法士など様々な職種と連携して働きます。
しかし、言語聴覚士の専門性が十分に理解されていないことから生じる、特有の「あるある」エピソードも存在します。
「STって何をする人?」という永遠の質問
新しい職場に入ったとき、必ずと言っていいほど聞かれるのが「言語聴覚士って具体的に何をするんですか?」という質問です。理学療法士は「足のリハビリ」、作業療法士は「手のリハビリ」と分かりやすく説明できるのに対し、言語聴覚士の仕事内容を簡潔に説明するのは意外と難しいものです。
「話すリハビリです」と答えても、「どんな風に?」と詳しく聞かれることが多く、結果的に長い説明になってしまうのは言語聴覚士あるあるの代表格と言われています。摂食嚥下障害への対応まで含めて説明すると、さらに複雑になってしまうのも特徴的です。
カンファレンスでの立ち位置の微妙さ
多職種カンファレンスでは、医師や看護師の発言時間が長く、リハビリ職種は後半になることが一般的です。その中でも言語聴覚士は、理学療法士や作業療法士よりも後に発言することが多いとされています。
「嚥下機能について」と発言しようとしたら、「それは栄養士さんからお聞きしましょう」と言われてしまった経験を持つ言語聴覚士も少なくないようです。摂食嚥下障害の専門性が十分に認知されていない現場では、こうした場面に遭遇することがあります。
他職種からの意外なオファー
「言語聴覚士さんなら文章が上手でしょう?」という理由で、病院の広報誌の原稿執筆や患者説明書の作成を依頼されることがあります。言語の専門家だからといって、必ずしも文章作成が得意とは限らないのですが、なぜか期待されてしまうのは職業柄仕方ないことかもしれません。
また、「発音がきれいだから」という理由で、院内放送のアナウンスを頼まれる言語聴覚士もいます。確かに話し方には気を遣っている人が多い職種ですが、放送の専門家ではないため、意外とプレッシャーを感じる業務の一つです。
職場での立ち位置に関するこれらのあるあるエピソードは、言語聴覚士の専門性をより広く理解してもらう必要性を示しているとも言えます。
続いて、日常生活の中で起こる言語聴覚士ならではの体験について紹介していきます。
プライベートで起こる言語聴覚士あるある
言語聴覚士の職業的な特性は、プライベートの場面でも発揮されることがあります。
家族や友人との会話、日常の買い物、テレビを見ているときなど、様々な場面で言語聴覚士の「職業病」とも言える行動や反応を示してしまうあるあるエピソードをご紹介します。
無意識に人の話し方をチェックしてしまう癖
テレビを見ていて、アナウンサーやタレントの滑舌が気になってしまうのは言語聴覚士の職業病の代表格です。「今の『さ』の音、少し不明瞭だったな」「舌足らずな発音だけど、それが魅力になってるな」など、ついつい専門的な視点で聞いてしまいます。
友人や家族との会話でも、相手の話し方を無意識に分析してしまうことがあります。「最近、早口になってない?」「もう少しゆっくり話した方が聞きやすいよ」といったアドバイスを、つい専門家モードで行ってしまい、「また始まった」と苦笑いされる経験を持つ言語聴覚士は多いようです。
食事中の観察眼が鋭くなる
摂食嚥下障害を扱う言語聴覚士は、無意識に人の食べ方を観察してしまう傾向があると言われています。家族が食事をしているときに、「もう少しよく噛んだ方がいいよ」「飲み込みのタイミングが早いかも」といった指摘をしてしまい、食事の雰囲気が微妙になることもあります。
レストランで隣の席の高齢者が食事をしている様子を見て、「大丈夫かな?」と心配になってしまうのも、この職業ならではの特徴です。職業柄、嚥下の様子に敏感になりすぎて、外食を純粋に楽しめなくなることもあるようです。
こどもの言語発達に敏感すぎる反応
言語聴覚士が親になったとき、自分のこどもの言語発達に過度に神経質になってしまうケースがあります。「もうこの年齢なのに二語文が出ない」「語彙が少ないかもしれない」など、専門知識があるゆえに心配しすぎてしまうのです。
友人のこどもと会ったときも、年齢に対する言語発達の程度を無意識に評価してしまい、「この子の発音、少し気になるな」と思っても、立場上なかなか直接的には言えずもどかしい思いをすることも少なくありません。
プライベートでのこれらの体験は、言語聴覚士という職業が日常生活にまで影響を与えていることを示しています。
次に、業界特有の悩みや課題について触れていきましょう。
言語聴覚士業界特有の悩みあるある
言語聴覚士として働く中で、この職業特有の悩みや課題に直面することがあります。
他の医療職種と比較して人数が少ないことや、専門性の認知度の問題など、言語聴覚士の業界全体に関わる「あるある」な悩みも存在します。
求人数の少なさと就職活動の難しさ
理学療法士や作業療法士と比べて、言語聴覚士の求人数は限られているのが現実です。特に地方では、「言語聴覚士募集」という求人を見つけること自体が困難な場合があります。転職を考えても選択肢が少なく、「今の職場を辞めたいけど、次が見つからないかも」という不安を抱える言語聴覚士は少なくありません。
新卒採用でも、「理学療法士・作業療法士募集」という求人は多く見かけるのに、言語聴覚士は含まれていないことがよくあります。面接に行っても、「言語聴覚士の方はあまり採用したことがないので」と言われてしまう経験を持つ人も多いようです。
一人職場の孤独感
小さな病院や施設では、言語聴覚士が一人だけということが珍しくありません。専門的な相談をしたいときや、判断に迷ったときに、同職種の同僚がいないため孤独感を感じることがあります。「これで良いのかな?」と不安になっても、すぐに相談できる相手がいないのは、この職業特有の悩みです。
研修会や勉強会も、理学療法士や作業療法士向けのものと比べて開催数が少ないとされています。スキルアップの機会を求めても、選択肢が限られているのが現状です。
専門性の理解不足による業務範囲の曖昧さ
「言語聴覚士って話すリハビリでしょ?」という認識のため、摂食嚥下障害や高次脳機能障害への専門的なアプローチが理解されにくいことがあります。その結果、本来の専門業務以外の仕事を振られたり、逆に専門性を活かせる業務から外されたりすることもあるようです。
また、診療報酬上の制約により、言語聴覚士が行いたいと思う訓練や評価が十分に実施できない場面もあります。患者さんのために最適なアプローチをしたくても、制度的な壁に阻まれることがあるのは、多くの言語聴覚士が感じている課題です。
これらの業界特有の「あるある」は、言語聴覚士という職業の現状を反映している部分もありますが、徐々に改善されつつある分野でもあります。
最後に、言語聴覚士の仕事で感じる喜びや達成感について触れてみましょう。
言語聴覚士だからこそ味わえる喜びのあるある
様々な課題や悩みがある一方で、言語聴覚士という職業には他では味わえない特別な喜びや「あるある」があります。
患者さんの回復過程に深く関わることで得られる感動や、専門性を活かして人の役に立てる充実感は、この仕事を続ける大きな原動力になります。
「初めての一言」に立ち会える感動
失語症の患者さんが、訓練を重ねて初めて意味のある言葉を発した瞬間に立ち会えるのは、言語聴覚士の特権です。家族の名前を呼べたとき、「ありがとう」と言えたときの患者さんとご家族の表情は、何度経験しても心を打たれるものがあります。
構音障害の患者さんが、正確な発音で話せるようになった瞬間も同様です。「こんにちは」という挨拶が明瞭に言えるようになっただけで、患者さんの自信と表情が劇的に変わることがあります。そんな変化を間近で見られるのは、言語聴覚士ならではの喜びです。
摂食機能の改善で「食べる楽しみ」を取り戻すお手伝い
嚥下障害のある患者さんが、安全に食事を摂れるようになることで、生活の質が大きく向上します。「また好きなものが食べられる」という喜びを患者さんが表現してくれたとき、言語聴覚士として大きな達成感を感じることができます。
経管栄養から経口摂取に移行できた患者さんが、「久しぶりにお茶の味がわかった」と涙を流しながら話してくれる場面は、摂食嚥下分野を専門とする言語聴覚士にとって最も嬉しい瞬間の一つです。
家族からの感謝の言葉
患者さん本人からの感謝はもちろんですが、ご家族からいただく感謝の言葉も言語聴覚士にとって大きな励みになります。「また会話ができるようになって、家族の時間が戻ってきました」「食事を一緒に楽しめるようになって本当に嬉しいです」といった言葉は、専門職としての使命感を再確認させてくれます。
退院後に患者さんやご家族が近況報告に来てくれることもあります。「あの時の訓練のおかげで、今でも調子良く過ごせています」という報告を受けると、言語聴覚士としてのやりがいを実感できるものです。
言語聴覚士の「あるある」エピソードは、この職業の魅力を物語っているとも言えるでしょう。
課題や悩みもありますが、患者さんの回復に寄り添えることで得られる喜びや達成感は、他の職業では味わえない貴重な体験です。これらの「あるある」に共感できる方は、きっと言語聴覚士という職業に誇りを持って取り組んでいることでしょう。