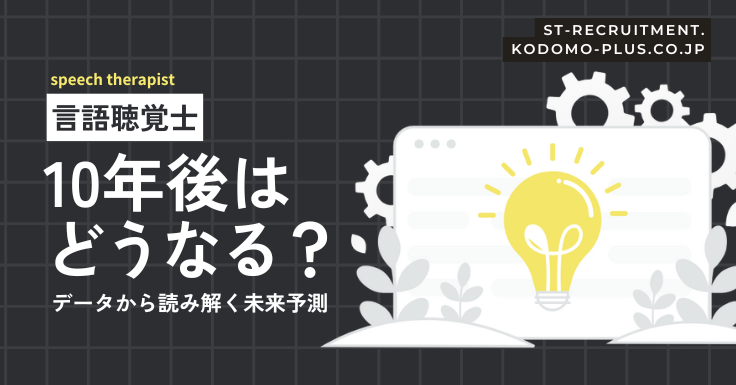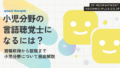近年、AI技術などが急速に進化する中で「この仕事の10年後はどうなっているんだろう?」と考えたことはありませんか?
日々変化する医療・福祉の現場で、言語聴覚士の10年後を見通すことは簡単ではありませんが、現在のデータを丁寧に分析することで、ある程度の予測は可能です。
今回は、言語聴覚士の10年後を具体的に予測し、現在から準備できることをわかりやすくお伝えします。
言語聴覚士が10年後も安定して働ける理由
言語聴覚士の10年後を考える上で、まず知っておきたいのは「人手不足がさらに深刻になる」という予測です。
現在でも言語聴覚士は全国で大幅に不足していることが報告されており、この状況は10年後もまず改善されないと考えられています。
具体的な数字を見てみましょう。
言語聴覚士の国家試験に毎年合格するのは約1,700人です。一方で、理学療法士は約10,500人、作業療法士は約4,700人が毎年新たに資格を取得しています。つまり、言語聴覚士は他のリハビリ職と比べて、新しく働き始める人の数が圧倒的に少ないのです。
さらに注目したいのは、国家試験の合格率です。理学療法士と作業療法士の合格率は毎年80%前後で安定していますが、言語聴覚士は約70%とやや低い水準になっています。この差は、言語聴覚士の専門性の高さを示していますが、同時に新しい人材の供給が限られることも意味しています。
実際に、ある大学では言語聴覚士の求人倍率が74.4倍に達したという報告もあります。これは、1人の卒業生に対して74件以上の求人があるということで、いかに言語聴覚士が求められているかがわかります。
この状況から言語聴覚士の10年後を予測すると、現在よりもさらに選択肢の多い働き方ができるようになると考えられます。
給与や働き方、職場環境など、様々な条件で仕事を選べるようになる可能性が高いのです。
次に、10年後の言語聴覚士の就職先について考えていきます。
10年後に大きく変わる言語聴覚士の働く場所
言語聴覚士の10年後を大きく左右するのが、高齢化のさらなる進行です。
2025年には団塊の世代がすべて75歳以上になり、2035年までの10年間で75歳以上の人口は約400万人増加すると予測されています。
高齢者ケアの現場が急拡大
75歳以上の高齢者は、脳卒中や認知症、飲み込みの問題(摂食嚥下障害)を抱える割合が高くなります。
厚生労働省のデータによると、脳血管疾患の患者さんの約半数が75歳以上であることからも、言語聴覚士が対応する患者さんの数が大幅に増えることは確実です。
脳卒中や認知症は、言語聴覚士が専門とする障害を直接引き起こす病気です。
脳卒中を発症すると、脳の言語中枢や運動機能が損傷されることで、失語症や構音障害、摂食嚥下障害といった症状が現れます。失語症では言葉が出てこない、相手の話が理解できないといった状態になり、構音障害では発音がはっきりしなくなります。また、摂食嚥下障害により飲み込みがうまくできず、むせたり誤嚥を起こしたりするリスクが高まります。
認知症の場合も同様で、病気の進行とともにコミュニケーション能力が低下し、会話が成り立たなくなったり、食べ方がわからなくなったりします。
特に注目したいのは「オーラルフレイル」という新しい概念です。これは、お口の機能が少し衰えることから始まって、食欲低下→栄養不足→筋力低下→活動量減少という悪循環に陥ることを指します。この考え方が介護保険制度に本格的に組み込まれると、全国の地域包括支援センター(約5,000箇所)や市町村の保健センターで、言語聴覚士の需要が急増する可能性があります。
つまり、言語聴覚士の10年後は、従来の病院での仕事に加えて、地域の高齢者が元気でいられるよう支援する「予防的な仕事」が大幅に増えると予想されます。
こどもの発達支援の需要も急増
もう一つ、言語聴覚士の10年後に大きな影響を与えるのが、発達障がいのあるこどもへの支援ニーズの拡大です。
発達障がいに対する社会的認知が向上している中で、特別支援学級に在籍するこどもの数は2013年の約18万人から2023年には約35万人へと、10年間で約2倍に増加しています。この増加傾向が続けば、2034年には約50万人に達する可能性があります。
このような状況の中で、言語聴覚士の10年後の働き方も大きく変わります。
従来の療育センターや病院での個別訓練だけでなく、学校を巡回して先生方にアドバイスをしたり、教育委員会で直接働いたりする機会が増えると考えられます。
小児分野の言語聴覚士については、以下の記事で詳しく解説しています。
小児分野で活躍する言語聴覚士とは?必要なスキルやキャリアについて
10年後の言語聴覚士のAIと遠隔リハで広がる働き方
言語聴覚士の10年後を語る上で欠かせないのが、AI(人工知能)や遠隔医療技術の発達です。
ただし、これは「AIに仕事を奪われる」という話ではありません。むしろ、AIと一緒に働くことで、より多くの患者さんに質の高いサービスを提供できるようになると考えられています。
現在すでに、失語症のリハビリテーション用のAIアプリや、認知機能を鍛えるソフトウェアなどが開発されています。これらの技術の特徴は、反復練習を自動で行い、患者さんの成績を詳しく記録・分析してくれることです。
例えば、従来は言語聴覚士が手作業で「正解率は○%でした」「今日は集中できていました」といった記録をつけていましたが、AIシステムなら正答率、反応時間、間違いのパターンなどを自動的に、そして正確に記録してくれます。
この変化により、言語聴覚士の10年後の仕事内容は「訓練を実施する人」から「データを分析して最適な治療方針を決める人」へと変わっていく可能性があります。
単純な反復練習はAIが担当し、人間にしかできない複雑な判断や、患者さん・ご家族との関係づくりに、より多くの時間を使えるようになるのです。
・その内容が本当にその人に合っているか?
・患者さんやご家族が安心して取り組めるか?
・現場の状況にきちんと合っているか?
といった判断は、人間の専門家にしかできません。
つまり、AIは「便利なアシスタント」ですが、最終的な責任を持ち、患者さんに合った形に調整するのは専門家です。今後はチェックだけでなく、AIを上手に使いこなしながら、より人に寄り添った支援をしていくことが求められます。
また、遠隔リハビリテーション(テレリハビリ)の普及により、自宅にいながらリハビリを受けられる環境も整ってきます。これは患者さんにとって便利なだけでなく、言語聴覚士にとっても地理的な制約なく、より多くの方にサービスを提供できる機会となります。
言語聴覚士が10年後に向けて今すべき5つの準備
言語聴覚士の10年後にはデジタル技術との協働が必須になると予想されるため、今からできる範囲で慣れておくことが大切です。
1. デジタル技術に慣れ親しむ
いきなり難しいプログラミングを学ぶ必要はありません。まずは、身近で役立つ基本的なスキルから始めてみましょう。
たとえば、オンライン会議システム(ZoomやTeamsなど)をスムーズに使えるようになることは、遠隔でのカンファレンスや患者さんへの指導にすぐ活かせます。さらに、Excelでデータを整理したりグラフを作成したりする力も、情報を分かりやすく伝えるうえで欠かせません。
加えて、新しいリハビリ用アプリやツールが登場したときに、その有効性を見極められる力を少しずつ身につけておくと、今後の臨床現場でも強みになります。
2. 他職種との連携スキルを磨く
医療や福祉の現場は、一人の患者さんを中心に「チーム」で支えることが増えていきます。
たとえば在宅医療や地域包括ケアの場では、ケアマネジャー、訪問看護師、リハ職、ヘルパー、さらには保健師や民生委員など、多職種が関わります。
このときに大切なのは、言語聴覚士が「自分の専門性をどう役立てられるのか」をチームに伝える力です。医師に対しては医学的な観点から、介護職の方には日常ケアの工夫として、と相手に合わせて説明できると連携がスムーズになります。
今からできることとしては、現職場で他職種と話す機会を積極的につくることです。
たとえばカンファレンスで意見を共有したり、ちょっとした場面で仕事内容を聞いてみたりするだけでも、相互理解は深まります。こうした積み重ねが、将来の地域連携に直結します。
3. 成長分野での専門性を深める
今後需要が拡大する分野での専門性を、今のうちから深めておくことをお勧めします。具体的には以下の分野が有望と考えられます。
前の章でもお伝えしたように、高齢者の摂食嚥下障害や小児発達支援は、今後ますます需要が高まる分野です。
ただし、すべての分野に手を出すのではなく、自分の興味や強みを活かせる分野を1〜2つ選んで集中的に学ぶことが効果的です。
4. 指導・相談スキルを身につける
直接的な訓練に加えて、他の専門職や家族への指導・相談の機会が大幅に増えると予想されます。
例えば、看護師や介護職員に安全な食事介助の方法を教えたり、ご家族にコミュニケーションのコツをお伝えしたりする場面が増えるでしょう。
現在の仕事でも、患者さんやご家族への説明、他職種への助言の機会を意識的に活用して、わかりやすく伝える技術を磨いてみてください。また、後輩指導の経験も、将来的に役立つスキルです。
5. 柔軟なキャリアプランを検討する
言語聴覚士の10年後は、従来よりもずっと多様な働き方が可能になると予想されます。
病院での常勤勤務だけでなく、複数の職場での非常勤勤務、訪問リハビリでの独立開業、フリーランスとしての活動なども現実的な選択肢となるでしょう。
今すぐ転職や独立を考える必要はありませんが、将来的な選択肢を広げるために、事業運営の基本知識や関連する法律について情報収集を始めることをお勧めします。
また、現在の職場でも管理業務やプロジェクトリーダーの経験を積むことで、将来の様々な働き方に活かせるスキルが身につきます。
10年後のキャリア設計を意識しよう
言語聴覚士の約8割は女性で、20〜30代が中心です。そのため、出産や育児と両立しやすい働き方をどう確保するかは大きな課題といえます。
今後10年で言語聴覚士も在宅勤務や短時間勤務など柔軟な働き方が広がる可能性はありますが、現状では制約も多いため、ライフイベントを見据えたキャリア設計が欠かせません。
ここまで、言語聴覚士の10年後について様々な角度から分析してきました。
結論として、10年後も言語聴覚士は社会に不可欠な存在であり、より多くの場面で求められることが予測されます。
今から準備を始めることで、変化に柔軟に対応しながら自分らしいキャリアの選択肢を広げることができます。未来の専門職としての可能性を最大限に引き出していきましょう。