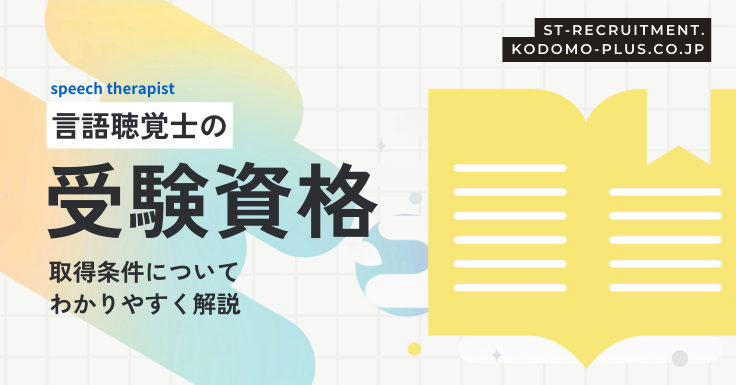言語聴覚士の国家試験を受けるには、まず受験資格を満たしていることが欠かせません。
「どうすれば受験できるの?」「自分の学歴でも大丈夫?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
言語聴覚士の国家試験は、定められた養成課程を修了することで受験資格が得られるとされており、高校卒業だけでは受験できないという特徴があります。
この記事では、言語聴覚士の受験資格について、学歴や年齢に応じた最適な取得ルートまで詳しく解説していきます。
言語聴覚士とは?
言語聴覚士とは、話す・聞く・食べるといった人間の基本的な機能に障害がある方のリハビリテーションを行う専門職として位置づけられています。
失語症や構音障害、摂食嚥下障害などの治療・支援を通じて、患者さんのコミュニケーション能力や生活の質の向上を目指すのが主な仕事内容とされています。
この職業に就くためには、厚生労働大臣が認定する国家資格である言語聴覚士免許の取得が必須と定められており、毎年2月に実施される国家試験に合格する必要があると言われています。
言語聴覚士の国家試験の受験資格とは?
言語聴覚士の国家試験を受けるための受験資格は、厚生労働省が指定する養成課程を修了することが絶対条件とされています。
高校卒業の学歴だけでは受験資格は得られないため、専門的な教育を受ける必要があると規定されています。
具体的には、文部科学大臣が指定する学校または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所において、3年以上(大学は4年)の課程を修了することが求められています。
この養成課程では、解剖学・生理学・心理学などの基礎科目から、言語学・音声学・聴覚障害学などの専門科目、さらに臨床実習までが含まれているとされています。
養成課程の修了要件は厚生労働省令によって厳格に定められており、単位不足や実習未完了の場合は受験資格が得られないという点も重要なポイントです。
言語聴覚士国家試験の受験資格は、厚生労働省が指定する養成課程を修了することが受験への必須条件となります。
言語聴覚士の受験資格を得る4つのルート
言語聴覚士の受験資格を取得するルートは、現在の学歴や社会人経験によっていくつかの選択肢があると考えられています。
以下の表で主要なルートを比較してみましょう。
| ルート | 対象者 | 修業年限 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 4年制大学 | 高校卒業者 | 4年 | 幅広い教養科目も学習可能 |
| 3年制専門学校 | 高校卒業者 | 3年 | 実践的なカリキュラムに特化 |
| 2年制専門学校 | 大学卒業者 | 2年 | 最短での資格取得が可能 |
| 学士編入 | 大学卒業者 | 2-3年 | 大学によって年限が異なる |
4年制大学(高校卒業者向け)
高校を卒業した方が4年制大学の言語聴覚関連学科に進学すると、専門科目に加えて心理学や社会学、福祉学など幅広い一般教養も学ぶことができます。学習期間が4年間と長いため、専門知識をじっくり体系的に身につけられるのが特徴です。卒業時には学士の学位が授与され、臨床現場での活躍はもちろん、大学院進学や研究者としてのキャリア形成にも有利に働きます。
3年制専門学校(高校卒業者向け)
高校卒業者が3年制の専門学校に進学する場合、一般教養は最小限に抑え、SLHTとしてすぐに活躍できる専門知識や技術の習得に重点を置いたカリキュラムが組まれています。学習期間が3年間で済むため、4年制大学より1年早く臨床現場に出られ、早期にキャリア形成が可能です。多くの学校では国家試験対策や就職支援も早期から手厚く行われます。
2年制専門学校(大学卒業者向け)
すでに大学を卒業して学士の学位を持つ方は、2年制の専門学校のSLHT養成課程に進むことで、最短で資格取得を目指すことができます。一般教養課程は既に修了しているため、2年間で専門科目に集中して学べます。このルートは社会人経験者のキャリアチェンジにも向いており、夜間部を設置して働きながら学ぶことも可能です。
学士編入(大学卒業者向け)
大学を卒業した方は、学士編入制度を利用して2~3年間でSLHT養成課程に進むこともできます。編入先の大学によって修業年限は異なりますが、すでに一般教養課程を修了しているため、専門科目に集中的に取り組める点は2年制専門学校と同様です。社会人や他分野からの転身を考える方にとって、効率的に資格取得を目指せるルートです。
言語聴覚士の受験資格は通信教育では取得できない
なお、言語聴覚士の資格は通信教育だけでは取得できません。
その理由は、この職種の業務が「対面でのコミュニケーション」「口腔器官の動きの評価」「身体への介入を伴う訓練」など、実践的な技能を中心としているからです。
これらは座学では身につかず、実際の臨床現場で行う長期の実習(臨床実習)を通じて習得する必要があります。
そのため、すべての養成課程で対面授業と臨床実習が必修とされており、通信制による資格取得は認められていません。
ご自身の状況に合わせて言語聴覚士の受験資格取得を目指しましょう。
次に、よくある疑問とその解決策について詳しく解説していきます。
受験資格についてよくある疑問と解決策
言語聴覚士を目指す方に向けて、受験資格に関するよくある疑問とその解決策をご紹介します。
社会人が言語聴覚士を目指すことは可能?
「30代や40代からでも言語聴覚士を目指せるのか」という質問がよく聞かれますが、年齢制限は設けられていないため、何歳からでもチャレンジ可能とされています。
実際に、子育てがひと段落した女性や、他業種での経験を積んだ男性が養成校に入学するケースも珍しくありません。
社会人の場合、経済面での負担を軽減するため、教育訓練給付制度や各種奨学金制度の活用が推奨されています。
一部の専門学校では、大学卒業者向けに夜間部や昼夜間部の養成課程を設置しています。
夜間部(平日夜間)や昼夜間部(平日夜間+土曜昼間)を利用すれば、日中に働きながら座学や学内演習を受けることが可能です。
しかし、ここで最大の壁となるのが「臨床実習」です。
臨床実習は、言語聴覚士になるために必ず履修する必修科目で、病院や福祉施設などの現場で数週間〜数か月(例:12〜15週間)行われます。実習は施設の稼働時間に合わせて日中に行われるため、夜間に行うことはできません。
そのため、働きながら学ぶ場合でも、臨床実習の期間中は仕事を完全に休むか、休暇を取得する必要があります。
「夜間部に通えば仕事を辞めずに言語聴覚士の資格が取れる」と考えるのは少し誤解があります。実際には、実習期間中の収入減や無収入の期間をどう乗り越えるかという経済的・時間的な計画が不可欠です。
他の医療系資格との関係
看護師や作業療法士、理学療法士などの医療系資格を既に持っている場合でも、言語聴覚士の養成課程を改めて修了する必要があると定められています。
例えば、看護師や理学療法士、作業療法士などの資格を持つ方が言語聴覚士を目指す場合、養成校によっては、これらの資格で習得した科目が一部免除されることがあります。このような免除制度を利用することで、学習期間を短縮できる可能性があります。
しかし、免除される科目や条件は養成校やカリキュラムによって異なるため、具体的な情報は各養成校に直接確認することが重要です。
入学前に詳細を確認し、必要な手続きを行うことで、効率的に受験資格を取得できます。
保育士資格を持つ方の場合、発達障がい児への支援経験が言語聴覚士の業務と関連性が高いものの、受験資格取得のための特別な優遇措置はないというのが現状の課題となっています。
受験資格を得るための学校選びのポイント
言語聴覚士の養成校選びでは、指定校以外で学習しても受験資格は得られないため、この点は特に注意が必要です。
まず、厚生労働省または文部科学省の指定を受けた正式な養成機関であることの確認が必須です。
養成校を選ぶ際の3つのポイント
養成校を選ぶ際の判断基準として、国家試験合格率が最も重要な指標の一つです。
過去3年間の平均合格率が80%以上の学校が一般的に推奨されており、90%を超える学校は特に優秀と評価される傾向にあります。
実習体制の充実度も重要なポイントと考えられています。
臨床実習は受験資格取得の必須要件であり、実習先の種類や数、実習指導体制の質が学習効果に大きく影響するとされています。病院だけでなく、介護施設や特別支援学校など多様な実習先を確保している学校が望ましいと言われています。
立地条件や学費についても現実的な検討が必要です。
3年間または4年間の通学が必要であるため、交通アクセスや生活環境を十分に考慮して選択することが推奨されています。
受験資格取得後の流れと国家試験の概要
養成課程を修了すると、言語聴覚士国家試験の受験資格が得られるとされています。国家試験は毎年2月に実施され、筆記試験のみで実技試験はないという特徴があります。
試験科目と内容
言語聴覚士国家試験は、基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音響学、言語学、社会保障制度等に関する問題が出題されます。
言語聴覚士の国家試験は、合計200問から構成され、すべて5つの選択肢から1つを選ぶマークシート方式で行われます。
試験は1日で完結し、午前と午後に分かれてそれぞれ100問ずつ出題されます。
試験時間は各150分、合計で5時間にわたって実施されます。
単純計算すると1問あたりに使える時間は約90秒となるため、幅広い知識を正確に理解していることに加えて、限られた時間の中で効率よく解答していくスピードと判断力も求められます。
合格基準は総得点の60%程度で、200点満点中120点以上が基準となります。
年度によって不適切問題の扱いなどにより基準点がわずかに変動することがありますが、原則として60%前後が合格ラインです。
試験では各分野ごとの得点基準は設けられていませんが、実際の臨床現場では幅広い知識が求められるため、全体的にバランスよく学習することが重要です。
受験手続きと注意点
受験申込は例年11月頃から12月頃にかけて行われ、養成校を通じて必要書類を提出することが一般的です。
第28回国家試験(2026年2月実施予定)は、願書の受付期間は2025年11月17日(月)から同年12月5日(金)までとなっています。
受験料は38,400円で、受験票は試験の約1か月前に送付されます。
2025年に実施された試験(願書の受付は2024年)では、1月29日に受験票が発送されました。
受験地は全国の主要6都市(北海道、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)に設けられ、原則として養成校の所在地に近い会場で受験することになります。
試験当日は身分証明書の持参が必須で、忘れると受験できない場合があるため注意が必要です。
免許申請から就業まで
国家試験合格後は、厚生労働省への免許申請手続きが必要です。必要書類の提出から免許証の交付までは約2か月程度かかると言われているため、就職活動のスケジュールに組み込んでおくことが重要です。
免許取得後は、病院・クリニック・介護施設・特別支援学校・発達支援センターなど多様な職場での就業が可能とされており、就職率は高い状況が続いていると報告されています。
言語聴覚士の就職先についてはこちらの記事で詳しく解説しています
言語聴覚士の受験資格取得は、現在の学歴や生活状況に応じて最適なルートを選択することが成功のポイントです。
まずは気になる養成校の資料請求や学校見学から始めて、自分の状況に最も適したルートを選択しましょう。